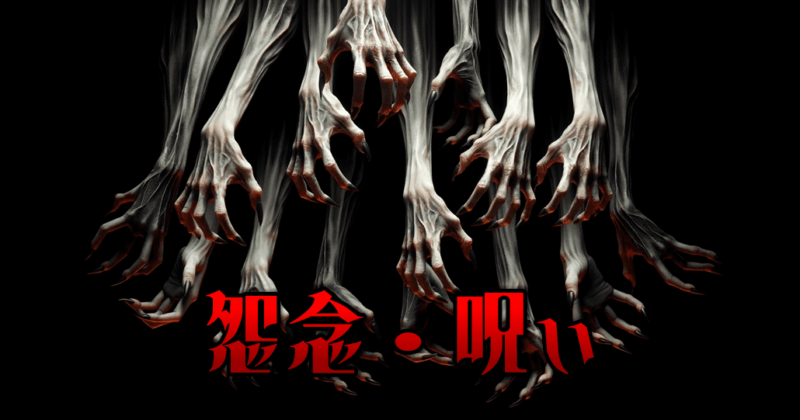
今の彼女と付き合い始めたばかりの頃の話。
とある駅前で彼女と待ち合わせをしていたのだが、その日は時間より早く着いてしまった。
近くに喫煙所があったのでそこで煙草を吸っていると、すぐ近くで黒人男性が露店の準備をし始めた。
並べているのは、カラフルなビーズで作られたネックレスやブレスレット。
どれも鮮やかな原色が多用されており、大ぶりなビーズが多く使われた派手なものばかりだ。
退屈なので横目で品物を見ていると、その黒人が視線に気付いて声をかけてきた。
黒人:「オニイサン、見テッテヨ。コレ、アフリカ本物ネ。ケニア、コンゴ、スーダン、イロンナ国ノヨ。安イ安イヨ」
いや俺そんなの付けないし、と断ろうとした時、運悪く彼女が来てしまった。
彼女:「お待たせー、あ、カワイイ!」
俺の顔もろくに見ないうちから、彼女の目は色とりどりのアクセサリーに釘付けとなった。
すぐに幾つかのネックレスを手に取ると、置かれた小さな鏡の前で自分の胸元に当て始める。
彼女:「最近フォークロアが流行りなんだよねー。私もこういうの一個欲しいなって思ってたんだ」
まずい流れだなと思っていると、案の定彼女はキラキラした笑顔で俺を見つめた。
彼女:「買って!」
俺:「やだよ、自分で買え」
彼女:「今日、記念日じゃん!買って!」
俺:「何の記念日だよ」
彼女:「付き合って、えーと・・・5週間ちょっと記念日!」
凄まじく半端な記念日を提示され、俺は言葉を失った。
俺の沈黙を勝手に肯定と判断した彼女は、どれにしよっかなーとひとしきり悩んだ後、ひとつのネックレスを手に取った。
「これ・・・」と呟いた後、笑顔だった彼女の顔から、すっと笑みが消えた。
その瞬間、俺は彼女が別人に変わってしまったかのような感覚を覚え、言いようのない不安を感じた。
彼女はどこかうつろな表情でネックレスを見つめたまま、「これにする。これがいい」と黒人に差し出した。
「アリガトネー、サンゼンエンネー」と言いながら、黒人がネックレスを袋に入れて彼女に手渡す。
正直俺は、このネックレスを彼女に買ってやりたくはなかった。
さっき感じた不安が頭を離れなかったからだ。
だが、黒人に「オニイサン、サンゼンエン」と真顔で催促され、俺は流されるまま金を支払ってしまった。
「ありがとう、大事にするね!」
そう言って振り返った彼女からは、先ほどの異様な雰囲気はすっかり消え失せていた。
結果的に上手く騙されたような気がしないでもなかったが、彼女はああいう妙な小技を瞬時に繰り出せるほど器用なタイプではない。
あの時の嫌な感じはただの気のせいだと自分に言い聞かせ、「今後、記念日は月一回だけな。それ以上は認めん」と彼女を小突いた。
夕食を摂ろうと入ったレストランで、注文の品が来るまでの暇つぶしに、彼女はさっきのネックレスを取り出し、さっそく首に掛けた。
「どう?似合う?」と笑ってみせる彼女は実に嬉しげだったのだが、胸元にかかったそのネックレスをまじまじと見直してから「あれ?」と首をかしげた。
彼女:「なんか思ったより地味。こんなだったっけ?」
そのネックレスはバッファローの角を楕円に削った黒と白の大きなビーズの間に、緑と黄色の小さなガラスビーズが交互に挟まれているだけのシンプルなデザインだった。
確かに、これ以外で彼女が手に取っていたのはもっと派手なものばかりだったので、俺も彼女がこれを選んだ時は意外に思ったのだ。
俺:「じゃあ、返品して他のに変えてもらわない?」
怖がらせたくはなかったので理由は明かさず遠回しにそう聞いてみたのだが、彼女の答えは「うーん、まぁシンプルな方が使い回しもきくし、これでいいよ」だった。
まあ、変な感じがしたのはあの時だけだったし、たいして気にするほどの事でもないかもしれない。
ちょうど頼んでいた料理が運ばれてきたのもあって、俺達はそこで話を打ち切った。
その夜、彼女の部屋で眠っていると、夜中に彼女が突然ガバッと飛び起きた。
その気配につられて俺も目が覚めた。
俺:「何、どうしたの」
眠い目をこすりながら彼女に尋ねると、彼女はしばらく俺の顔を見つめてから「・・・なんだっけ?」と訳の分からない質問で返してきた。
聞けば、怖い夢を見て飛び起きたのだが、内容をすっかり忘れてしまったのだという。
ああそう、と速攻で寝直す体勢に入った俺は、彼女にぶーぶー文句を言われながらも眠りに落ちていった。
それからほぼ毎日、彼女は悪夢にうなされるようになった。
目が覚めるといつも内容を忘れているのだが、泣きながら目覚めることもあった。
あのネックレスが怪しいと思った俺は、あの日感じた不安をついに彼女に打ち明けた。
俺:「だからさ、やっぱ捨てたほうがいいって。あれ買ってからじゃん、うなされるようになったの」
しかし、俺の主張に彼女は難色を示した。
彼女:「あれが原因とは限らないじゃん。違ってたらもったいないもん」
どうしても捨てるのは嫌だと言う彼女と折衝を重ねた結果、とりあえず何日か俺が預かってみることで話が付いた。
俺はネックレスを持ち帰り、彼女がしていたようにベッドの脇に置いて眠ってみたが、特に悪夢は見なかった。
だが、彼女の方は効果覿面だった。
ネックレスを手元に置かなくなってから、悪夢を見る事がなくなったのだ。
明らかな変化に、今度は彼女の方から処分を頼んできた。
彼女は俺が鈍感だから影響を受けないのだと茶化したが、「だからって普通に捨てたりしないで、ちゃんとした人にやってもらってね」と俺の身を案じてくれた。
俺は彼女の言葉に従い、神社で禰宜をやっている知人に処分をお願いした。
そのネックレスを見るなり、知人は「あー多分これ遺品」と言った。
詳しく話せと言われて経緯を話すと、なるほどねとうなずかれた。
知人:「前に似たようなの預かった事があって調べたんだけど、アフリカとかの貧困地域だと死者の遺品は遺族の大事な収入源なんだよ」
宗教観もあるのだろうが、手元に置いて故人の思い出に浸る事よりも、明日ご飯を食べる事の方がよほど大事なのだろう。
そんなわけで、遺品を安く買い取って物価の高い国に持ち込んで売ってるような露店ってのは結構あるそうだ。
最近だとネットオークションにも多いらしい。
一応「俺が影響を受けないのは鈍感だからですか」と聞いたら、「それもあるかもしんないけど」と大笑いされた。
知人:「まぁ多分、女性の方が影響受けやすいんじゃないかなぁ。霊が憑いてるというより『念が残ってる』って感じなんだけど、そういうのは女性の方が感じやすい。それにこれは女性の持ち物だっただろうから、同性の方が思いを共有しやすいのかもね」
モノが手元を離れれば問題ないとの事だったので、ネックレスだけ供養してもらう事になった。
かくしてアフリカの遺品ネックレスは、遥か極東の神社でお焚き上げ供養を受け、天へと還った。
輸入雑貨が持て囃される昨今だが、出処のはっきりしない物を買うという事のリスクを痛感した出来事だった。


