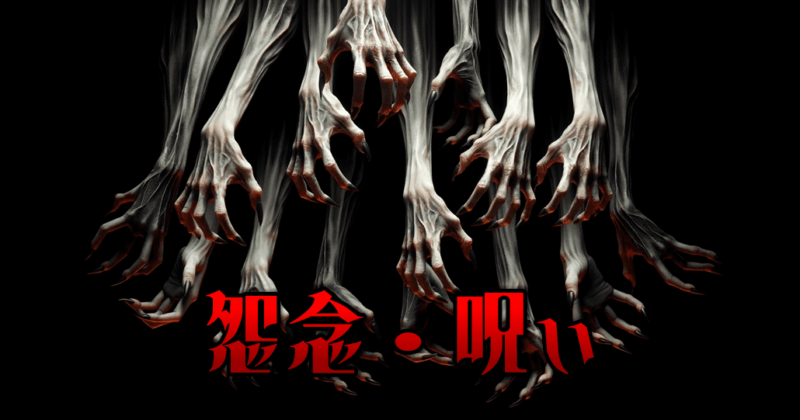
※長文
私が子供の頃の話だ。
夏も終わりに近づいた8月半ば、中学生だった私は友人のTと村で行われる夏祭りに遊びに出掛けていた。
私の村は山の中のド田舎で近くには遊べるものなど何もなく、年に一度の夏祭りが村唯一の楽しみであったからだ。
夏祭りには村の人々が総出で様々な出店を出す。
私達は綿菓子を片手に会場である神社の境内をぶらぶら徘徊していた。
「おっ。あれ見ろよ。」
Tが指を指す方を見ると、人だかりが目に入った。
「あ~、あの行事か~。何が面白くてあんなのに集まるんだろうな~。」
私の育った故郷には、不思議な信仰があった。
それは、包丁を『包丁様』と呼び、信仰し崇めると言うものである。
といっても全ての包丁を崇めると言うわけではなく、神社に納められている、錆びて赤茶けた古い包丁が信仰の対象であった。
毎年夏祭りの時期になると、年に一度だけこの包丁が寺から人前に姿を表し、神主がこの包丁で魚を裁くのだ。
この包丁信仰にはきちんとした理由がある。
昔、この村を大飢饉が襲った。
この村は周りに海もなく、他の村からも遠かったので村の中で生産していた食料で生活する他なく、飢饉の時には村の半分以上の人間が亡くなったらしい。
そこで村人達は飢饉を終わらせるために、料理の際に使う包丁を「食料の象徴」として崇め、また包丁を「膨腸」つまり腹一杯であるとして祈りを捧げたのである。
その結果なのか、飢饉は収束を迎え、村は平穏な生活を取り戻したのである。
・・・そう、その人だかりは神主が魚を裁く様子を見守る人々の集まりであった。
だが私達子供にとっては、重々しい空気の中オッサンが魚を裁くイベントなんて微塵も興味がなかった。
「ホント、何が面白いんだか。」
私がそう言うと、Tは「そうか?夏の恒例行事って感じで結構面白いけどな。」と思いがけないことを口にした。
「お前変わってるな・・・・・・。」
「そうかな?それよりさ、あの包丁、いつも遠くからちらっとしか見れないじゃんか。もっとじっくり見てみたいよ。」Tはあんなもののどこに興味があるのだろうか。
いわゆる「骨董品の好きなオヤジ」みたいなものだろうか・・・・・・。
「でも見るっつったって、どうするのさ。」するとTは自信満々の笑顔で答えた。
「実はさっき、神主が包丁を納める倉の鍵を落としたのを見付けて、拾ったんだよ。」Tの手にはリングに付けられた鍵の束があった。
「あの倉の鍵は南京錠でこの鍵がなくても閉められるから、神主も気付かないと思うよ。」Tはもうあの包丁以外に興味はないらしい。
「仕方ない。付き合ってやるよ。」
私は別に包丁なんかに興味はなかったが、いたずらっ子ではあったのでそういうスリルは大好物だった。
時計の針が11時を回った頃、私達はこっそり窓から家を抜け出し神社に集まった。
「親にはバレてないな?」
「うん、大丈夫。」
二人で確認しあい、人がいないか辺りを見回す。
祭りの片付けも終わり、騒がしかった神社の境内は一転して怖い位に静かになっていた。
聞こえてくるのは虫の声と、風の音ばかりである。
「じゃあ行こう。」
懐中電灯を片手に、私達は神社の隅にある倉に向かった。
倉は木造のものらしく、焦げ茶色の年期の入った厚い木の扉には南京錠がかけられている。
「開けるよ。」
Tは私にそう囁くと、鍵を使い南京錠を外した。
扉を開けると、風で黴臭い臭いと埃が舞い上がって私達の鼻に入った。
「ゲホッ!ゲホッ!」
私が思わず咳き込むと、Tは人差し指を立て「静かに!」と私に示した。
服の首もとを顔に当て、マスク代わりにしながら中に侵入する。
歩く度に「キィ・・・・・・・・・キィ・・・・・・・・・」と不気味に床が軋み、外気に比べ異様に冷たい倉の中の空気とも相まって私は総毛立つのを感じた。
しかし意地っ張りだった怖いとも言えず私はただTに着いていく他なかった。
「おっあったぞ!」
Tが嬉しそうに言った。
そこには綿の詰められた木箱に納められた、錆だらけの包丁が置かれていた。
俺はそれを見た瞬間、得体の知れない嫌な感じが身体中を駆け巡った。
まるで不幸の象徴のような、死神を目にしたような感覚である。
「なぁ・・・ヤバイってこれ・・・・・・」
俺が言うのも聞かずに、Tは包丁様を手に取ると顔を近づけまじまじと眺めた。
その目は輝いていた。
だがその光はただ好奇心や達成感からくるものだけではなく、ギラギラとしたその輝きは狂気の光を帯びているようにさえ感じられた。
「ふふふ・・・・・・・・・ふふふふふふふふふ・・・・・・・・・・・・」
突然Tは包丁を手にしたまま口許を歪め笑い始めた。
「どうしたんだ・・・・・・T・・・・・・おい!」
私は声を荒げて呼び掛けるがTの耳には届いていないようである。
Tは張り子のように首をカクカクと横に揺らし、包丁様を眺めている。
「ふ・・・・・・・・・ひひ・・・・・・・・・」
嫌な笑みを浮かべると、いきなりTは包丁様で自らの腕を切りつけた。
私は驚きのあまり、言葉を失った。
「ひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひ!」
Tの、聞いたこともない甲高い笑い声が狭い倉の中に響いた。
包丁の刃は錆び付いていたものの、まだ刃物の体は保っているため、切り付けられた腕からはじわりと赤い血が染みだしてきた。
Tは目を見開いて、舌を出してその血を啜った。
その顔はもはや人間のものではなく、『鬼』という表現が当てはまる程狂気に駆られた表情だった。
これはヤバい・・・・・・・・・・・・そう感じた私は咄嗟にTの持っている包丁様を叩き落とした。
包丁様は「ガチャァァァン!」と大きな音を立てて床に転がり落ちた。
「T!しっかりしろよ!T!!」
するとTはきょとんとした表情に変わり、「ん?どうした?」と何事もなかったかのように私の方を見て言った。
「とにかく!早くここから出よう!」
俺はまだここに居座ろうとするTを強引に倉から引っ張り出すと、逃げるように神社を後にした。
翌日は学校の登校日だった。
私は約1ヶ月ぶりに制服に着替え、学校へと走った。
教室に入ると、Tがいた。
いつもなら私と同じ位か遅れてくる位なのに、今日は既に授業道具を引き出しに入れて棚にバッグを納めていた。
「おはよう!」
Tに話しかけるも、Tは元気なく俯いたままである。
「・・・・・・・・・どうした?」
顔を覗き込もうとすると、Tはようやく私の存在に気付き顔を上げた。
「あぁ・・・おはよう・・・・・・」
Tは窶れた様子で、目の下には隈が出来ていた。
そしてその腕には、数え切れないほどの切り傷があった。
「なぁ・・・・・・その傷・・・・・・・・・」
俺が聞こうとすると、Tは誤魔化すように「何でもないよ!」と言って再び俯いた。
登校日とはいっても夏休みの真っ只中、あることと言えば全校集会と課外授業程度である。
私達は体育館に集められ、校長が話をするだけの退屈な集会が始まった。
段上にスーツを着た白髪の男性が立ち、ゴホン、と一回咳払いをすると口を開いた。
「え~皆さん。夏休みは元気に、安全に過ごせていますか。」
校長はいつもの決まり文句から話を始めた。
「え~・・・・・・昨日は夏祭りで・・・あ~楽しんだ方もいらっしゃると思いますが・・・・・・昨日深夜に・・・神社の倉庫の中に何者かが侵入するという事件がありました・・・・・・・・・え~わが校の中にそんな人はいないとは思いますが・・・・・・もし何か知っていましたら先生に・・・・・・きちんと言うように。」
そう言って校長は一礼すると歩き出した。
「おい・・・T・・・・・・」
私は小声でTに話し掛けた。
「どうしよう・・・・・・大事になってるみたいだ・・・・・・」
だがTは俺の話には耳を傾けず、俯いたままだった。
口許に、笑みを浮かべたまま。
やがて全校集会も終わり課外授業が始まった。
夏休みの工作として版画を作るというもので、私達は美術室で板との睨めっこを始めた。
さっきの校長の話を引きずってはいたが、少しでも真面目にすることで罪の意識を軽くしたかったのかもしれない。
Tは椅子に座ったまま外をぼんやりと眺めている。
まあ課外授業だし、しなければしないで夏休みの宿題が増えるだけだ。
私は黙々と作業をした。
ちょうど夏祭りの翌日だったこともあり、月並みに「夏祭り」を題材にした版画を製作することにした。
板に絵の下書きを書き終えると、次は彫刻刀で板を彫る作業である。
持参した彫刻刀セットから一番使いなれた三角刀を取りだし、右手に握り締めた。
太陽の光が刃先に反射し、私の目にその輝きが飛び込んできたその瞬間、私は不思議な感覚に教われた。
右手は自然に俺の左手に向かい、彫刻刀で腕の肉を切り裂いていた。
痛いとかそういう感覚はなく、ただこうしないといけない、そう思いながら腕を何度も何度も突き刺した。
「キャアアアアアアアアアアア!」
私を正気に戻したのは女子の叫び声だった。
気が付くとクラス全員が青ざめた顔で俺の方を見詰めている。
「ちょっと!大丈夫なの?」
先生が心配そうに駆け寄ってきた。
見ると、俺の腕は血だらけだった。
「いってえええぇぇぇぇぇぇぇ!」
そこで初めて私は腕の痛みを感じ、転げ回った。
すぐに私は保健室に連れていかれ、消毒を受けたあと包帯で腕をぐるぐる巻きにされた。
そういえばTも腕を怪我していた。
もしかしたら包丁様に触ったせいなのか・・・・・・・・・?
あの時俺が止めていれば・・・・・・後悔と、とんでもないことをしてしまったという罪悪感が胸を締め付ける。
「・・・・・・昨日、包丁様に触ったわね。」
突然、先生が鬼の形相で私を問い詰めた。
あまりに唐突だったので私は心臓が止まるかと思った。
「・・・・・・・・・・はい」
私は自分の犯した罪の意識と、怒られる事への恐怖から昨日あった事を洗いざらい話した。
私とTは校長室に連れていかれた。
Tは相変わらず生気のない顔つきだった。
中に入ると、そこにはスーツ姿の神社の神主、近所の寺の住職、そして教員一同が待ち構えていた。
全員、怒っているというより、心配しているといった表情をしていた。
「座りなさい。」
校長に言われ、私達は黒いソファーの上に座らされた。
前には寺の住職が座っていた。
「あの包丁様について・・・・・・ご存知ですか?」
唐突に住職は私達に尋ねた。
「はい。飢餓の時に村の人達が神様って崇めたって・・・・・・・・・」
「では何故それで村人は助かったと思いますか?」
「それは神がかった力が・・・・・・」
そう言いかけて、私はハッとした。
「気付きましたか?包丁とは本来、何をするものですか?」
「・・・・・・・・・食物を切るもの・・・」
「ええ。しかし飢餓によって食料は底をついた。では何を切ったと思いますか?」
「・・・・・・・・・・・人間・・・・・・・・ですか」
「はい。彼らは食料として、『人間』を食したのです。始めは死体からでした。生き残るためには仕方がないと・・・。しかし死体すら底をつき始め、彼らはとうとう生きた人間に手をつけ始めた。最初は老人、次に女子供、そうやって彼らは生を繋いだのです。だから包丁様は本来、神を扱う神社ではなく死人を供養する寺に預けられるべきものなのです。しかし村人達が自らの行為を正当化するために包丁を神と崇め、神への儀式として人間を殺した。だから包丁様は神社に納められているんですよ。」
すると今度は、横に立っていた神社の神主が話を始めた。
「毎年夏祭りで行われる儀式・・・・・・あれは包丁様に血を吸わせることで、少しでも祟りを抑えるためのものです。一度血の味を知った刃物は再び血を求めるようになりますから・・・・・・」
「つまり、包丁様は殺された人々の無念と呪い、そして血を求める刃物の力が合わさったとても危険なものなのです。とくに貴方。」
そう言って住職はTを指差した。
「貴方は直接包丁様に触れてしまった。そのせいで包丁様に魅入られてしまっているのです。このままだと包丁様は貴方だけでなく他の人間の生き血まで求めることになる。これから私の寺で貴方たちを守るために儀式を行いますが、成功するかはわかりません。貴方達の犯した罪の罰として重く受け止めてください。」
そういうと住職は私達を連れて車に乗り込み、寺へと向かった。
辺りが暗くなり始めた頃、私達は寺に到着した。
車から降ろされ辺りを見回すと、地べたには白い布が敷かれ、その正面にはあの木箱に入れられた包丁様が置かれていた。
「それでは、その布の上に正座してください。」
言われるがまま、私達は指示された場所に座った。
住職は剃刀を取り出すと、俺に手を出すように言った。
「痛いですが我慢してください。」
そう言うと、俺の腕に剃刀を当て、スッと切り傷をいれた。
じゅるりと傷口から血が滲み出る感触を感じた。
同様にTの腕にも傷を入れ、住職は包丁様の前に座った。
既に空は深い紺色に染まり、寺の中は昨日の神社のような夜の静寂が訪れている。
「いいですか?これから何が起きても、決して目を開けてはいけませんよ。」
そう言って住職は手を合わせ呪文のようなものを唱え始めた。
私達は言われたように目を閉じただ住職の言葉に耳を傾けていた。
住職の呪文は葬式で聞いたお経に良く似ていたが、所々で「血を」「無念」「臓物」という言葉が耳に入った。
私達は何も考えず、ひたすら住職の言うように瞼を閉じ続けた。
儀式が始まって1時間が経った。
未だに何の変化も起こらず、そろそろ退屈に感じていた俺の顔に、突然妙に生温かい風が吹き付け始めた。
そのとき、私を取り巻く周りの空気が一気に変わった。
ここに「悪いもの」がいるということが肌からビリビリと感じ取れた。
いきなり地獄に突き落とされたような気分だった。
生ゴミの腐ったような臭気がツンと鼻をつく。
耐えきれずに俺は薄目を開けてしまった。
そこには木の枝のように痩せ細った、髪の毛がボサボサで顔を隠すほどに伸びきった、まるで餓鬼のような人間がいた。
それはこの暗い寺の中でも細かい所まではっきりと見ることが出来た。
だが絵で見た腹のふくれた餓鬼のイメージとは異なり、腹は胸元から引き裂かれそこに内臓はなく、ただ骨と赤黒い肉が見えているだけだった。
「目を閉じてください!」
住職が叫ぶ。
私は目を開けたことを後悔し、ギュッと固く瞼を閉じた。
「ザッ・・・・・・・・・」
「ザッ・・・・・・・・・」
「ザッ・・・・・・・・・」
「ザッ・・・・・・・・・」
足音が聞こえた。
間違いなく、アレがこっちに向かってきている音だった。
「ザッ・・・・・・・・・」
「ザッ・・・・・・・・・」
「ザッ・・・・・・・・・」
足音は徐々に近付いてくる。
やがて足音は私の正面に来たところで止んだ。
「ハァァァァァァ・・・・・・・・・」
荒い息遣いとともにあの生臭い空気が、今度は直接顔にかかった。
吐き気がするのを押さえながら、私は必死に息を堪えた。
もう頭がどうにかなりそうだった。
しかし生きたいという思いから私はかろうじて自我を保っていた。
「ジュル・・・・・・・・・ジュル・・・・・・・・・」
腕に生暖かい感触を感じた。
どうやら奴は私の腕の血を舐め取っているらしい。
傷口の痛みで腕が痺れ出し、全身が恐怖のあまりガタガタとみっともなく震える。
それでも私は瞼を閉じ続けた。
「ハァァァァァァ・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
奴は顔を上げ再び息を吐いた。
そして足音とともに、奴の気配が移動していくのを感じた。
恐らくTの方に向かったのだろう。
私はそこで気を失った・・・・・・・・・。
気が付くと私は布団の中にいた。
そこは寺の中のようで、壁には掛軸が掛けられた、随分広くて立派な和室だった。
住職は部屋にはおらず、隣にはTが座っていた。
「起きたか・・・・・・・・・」
Tが心配そうに言った。
「ああ・・・・・・・・・」
私は重い頭を持ち上げ答えた。
疲れのあまりに目眩すら感じる。
すると扉の向こうから住職が現れ、私達に水の入ったコップを差し出した。
「何とか包丁様には帰って頂けました。貴方達の生き血を啜って満足していただけたのでしょう。」
「あれは・・・何なんですか・・・・・・」
「あれは飢饉の際に殺された者の怨念の塊です。腹の中身は全てえぐり出され、肉を喰われ、骨と皮だけの姿に成り果てた可哀想な人達です。」
私達が言葉を失い俯いていると、住職は優しく言った。
「大丈夫です。あの方達を供養するために、包丁様の儀式があるのですから。」
その後、私達は家に返され、何事もなかったかのように元の生活に戻ることができた。
ただ毎年行われる例の儀式だけはきちんと見守るようになった。
それが少しでも死者の供養になるのなら、そう思ったからである。
ただ、以前に比べて大きな怪我をすることは多くなったような気がする。
だがこれも、私達が死者を冒涜した罰として受け止める他ないのだろう。
あの日、住職は最後にこう言った。
「いいですか。食べ物とは人間にとってとても大事なものです。それだけは、忘れないでください。」


