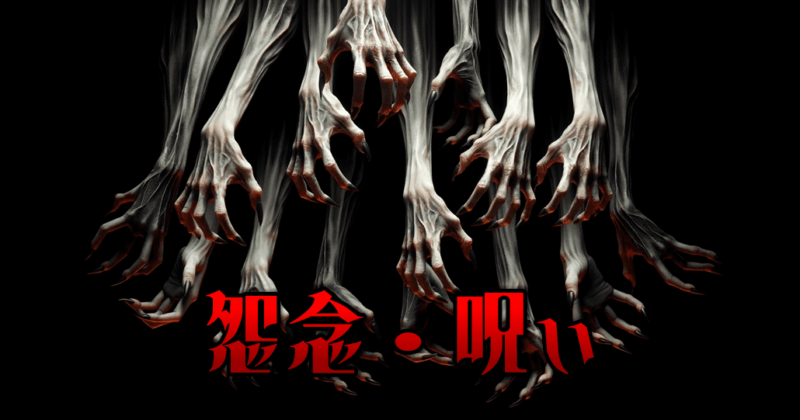
俺の体験した話。
俺のじいちゃん家は結構な田舎にあって、子供のころはよく遊びにいってた。
じいちゃんは地元でも名士?っていうのかな、土地を無駄にいっぱい持っててそれの運用だけで結構稼いでたらしい。
だからじいちゃんとばあちゃんはちっちゃな畑で自作するだけで暮らしてた。
土地をめぐってやくざとトラブルになることもあったけど・・・この話と関係あるかは判らん。
俺が小学5年生のときのこと。
俺と弟(二歳下)は毎年夏休みになるとじいちゃんちに1~2週間泊まるって習慣があった。
けど俺らはまだガキだったから、じいちゃんちの障子を破ったり、クレンザーまき散らかしたり、ひどいイタズラっかやってた。
俺の両親はそれに激怒して一度出入り禁止にされそうになったんだけど、じいちゃんたちは俺ら兄弟をえらく可愛がってたらしくて、やめるなって逆に両親を説得してた。
まあそれでその年も泊まりに来たんだけど、そのときの話。
じいちゃんちの家の裏には畑があって、その隣にちょっとした林(雰囲気は森)がある。
で、森の真ん中には池があって、鯉を飼ってた。
弟が釣り好きだったんで近くの湖で鯉を新しく釣ってきて入れることもあったんだけど、そんな時じいちゃんたちはえらく喜んでくれた。
まあ結構釣る→入れるって感じでがんがん追加してたんだけど、池が鯉で一杯になることは決してなかった。
じいちゃんたちは「猫が食べちゃうんだよ」って説明してたし、俺らもそれで納得してた。
あるとき、森の池を釣堀に見立てて釣りをしようって話になった。
俺は釣りに興味はなかったけど、じいちゃんたちに「裏の池には絶対一人で行くな」って言われてたから弟についていった。
俺んちは結構熱心な仏教徒で無益な殺生はタブーだったんで、釣りっていってもキャッチアンドリリースか鯉こくとかにして食うかが基本、子供ながら無駄に殺したりはしなかった。
で、一匹釣ったところで、俺が「鯉に洗剤掛けたらどうなるか実験しようぜ」というあほな実験コーナーを提案した。
俺の提案に大体は悪乗りしてた弟も賛成し、実験の結果、当然鯉は死んでしまった。
死んだ鯉を見て子供心にも多少罪悪感はあったけど、「ほっときゃ猫が食べるだろ」と思いそのまま放置して帰ることにした。
けど、ここで弟が「兄ちゃん、猫が鯉食うとこ見ようぜ」というこれまたアホな提案をした。
まあ俺も動物番組でライオンがシマウマを襲うシーンをカッコいいとか思ってたので生で見るのも悪い気はせず、近くの茂みに隠れて様子を伺うことにした。
しばらく潜んでると、森の奥側(畑と反対側)にある一番でかい木がガサガサと木の葉を揺らしだした。
当時俺は猫の生態を知らなかったので、「ああ猫は木の上に住んでるんだなー」と思いながらぼんやり見てた。
突然、隣にいた弟が「・・・猿」とつぶやいた。
俺は「へ?」と思いその木の上のほうを見上げると、確かに何かいた。
猫にしてはデカイ・・・。
今思い返すと、その獣は夏であるにもかかわらずやけに毛深かった。
その獣が、樹上から地上に向かって木の幹にへばりつくような感じで、「頭を下にして」降りてくる。
どことなく爬虫類を思い出させるような、いやな感じの動きだった。
その『なんだかよくわからないもの』は、ゆっくりと池に向かって歩いてきた。
俺はいつの間にか体が震えていることに気付いた。
隣を見ると、弟も顔を真っ青にして体を震わせている。
その生き物が近づいてくるにつれて、何か人の声のようなものが聞こえてきた。
耳を凝らすと、その獣が何かつぶやいている。
「・・・・・・・・・・・・・・・もの。・・・・・・・・・・・・・・・もの。・・・・・・・・・・・・・・・・・・もの。・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
なんだ?
何を言ってるんだ?
俺は当初の目的を忘れ、ここから逃げ出したくてたまらなくなった。
弟が一緒じゃなかったら、漏らしていたかもしれない。
そのくらい怖かった・・・。
やがてそのけものが近づいてきたときに、顔と呟きがはっきりと判った。
あれは人の顔だ!
しかも人間で言うとこの乳幼児くらいの。
そいつが無表情でつぶやいている言葉も聞き取れた。
「・・・いきるもの。・・・・・・・・・そだてるもの。・・・・・・・・・・・・・・・かりとるもの。」
「・・・いきるもの。・・・・・・・・・そだてるもの。・・・・・・・・・・・・・・・かりとるもの。」
そして、鯉のところまで来ると、その鯉を見下ろし、ニタリ、と嫌らしい笑みを浮かべた。
「これで・・・・・・できる。」
そう言って、鯉には手をつけずに帰っていった。
俺ら兄弟はしばらく動けなかった。
呆然、という表現が正しいかもしれない。
我に返ると、いつもは使わない裏口への抜け道ルートを使って森を抜け、家まで辿り着いた。
さすがの俺らのこの出来事には参って、夕食の時には元気がなくて、飯ものどを通らなかった。
心配したばあちゃんが「どうしたの?」って聞いてきたけど、俺は何にもないよって答えるよりほかなかった。
けど弟はついに耐え切れなくなったのか「ねえ兄ちゃん、やっぱりあの猿・・・」と口走ってしまった。
その瞬間、じいちゃんがさっと顔色を変えたのがわかった。
人の顔があんなにわかりやすく変わったのは、後にも先にもそのときだけだと思う。
じいちゃんはなんだか怒ったような感じで「どういうことだ」と問い詰めてきた。
俺たちが観念して昼間のことを話すと、今度はばあちゃんと顔を見合わせて、心配そうな顔で「気分はどうだ、なんともないか」ってしつこく俺と弟に聞いてきた。
ああ、やっぱり怒られるんだろうか・・・と俺が不安だった俺は、正直戸惑った。
じいちゃんはおもむろにどこかへ電話をかけ始めた。
俺と弟は玄関口に連れ出され、ばあちゃんにビンの酒をいやというほど浴びせられた。
そして子供の砂かけ遊びみたいに塩をまかれた。
電話を掛け終わったじいちゃんは俺たちのところへやってきて、とても真剣な表情で「もうお前たちをこの家に上げるわけにはいかん。俺たち(じいちゃんたち)が生きている間は、決してこの家へは来るな」と言った。
弟は突然の拒絶に「どうして?どうして?」と言って泣き喚いた。
俺もじいちゃん家が好きだったから、とても悲しかった。
俺たちが落ち着くと、じいちゃんは「それはな、お前らがこの土地の守り神を怒らせてしまったからだ。守り神っていっても、うちにおる仏さんみたいな優しいもんじゃない。」といって、俺たちにしばらく説明してくれた。
要点をまとめると、昔この土地に住み着いた先祖が神様に生け贄を捧げて、末代の祟りと引き換えに富を手に入れたこと。(狗神憑きみたいな感じ)
うちで殺生が禁じられているのは、仏の教えというよりもその神さまに付け入る隙を与えないためであるということ。
もし神さまを起こした場合は、誰かが犠牲になってこの土地に縛られ、祟りを受けて鎮めなければならないこと。
・・・などを説明してくれた。
話のあとで、じいちゃんは「今夜だけは帰れん、けど安心しろ、じいちゃんたちが守ってやるから、
明日朝一番に帰るんだ」といって、その日だけは泊まることになった。
やがてじいちゃんの電話の相手が来た。
俺の見知らぬ女の人で普通のおばちゃんに見えたけど、あとから聞いた話では、土地ではかなり有力な霊能力者らしい。
おばちゃんは俺たち兄弟を一目見るなり「あら、これは大変なことになっちょるね。ともかくこれをもっときなさい」といってお札を一枚ずつ渡してくれた。
姿の見えなかったばあちゃんは寝室の準備をしていたらしく、俺たちは仏間に泊まることになった。
仏間は小さな部屋で、一つだけある窓も新聞紙で目張りされていた。
そこには布団が二つと、普段はないテレビ、お菓子などの食料が用意されていた。
じいちゃんは俺たちに「いいか、これからお前たちは二人だけで夜を越えなければいかん。その間、じいちゃんもばあちゃんもお前らを呼ぶことは決してない。いいか、なんと言われても、絶対にふすまは開けるなよ。」と念を押した。
俺たちは怖かったからじいちゃんたちに一緒に寝て欲しかったけど、そういうわけにはいかないらしい。
ともかく、二人だけで寝ることになった。
はじめのうちはテレビを見たり話したりして過ごしていた俺らも、だんだんと疲れが出てきて、いつの間にか眠ってしまった。
目が覚めたのは、何時ごろだったろうか。
まだ、あたりは暗かった。
なぜ起きたんだろうとぼんやり考えていると、外でがさがさと物音が聞こえた。
それとともに、あのつぶやきも聞こえる。
「・・・・・・・・・・・・・・・もの。・・・・・・・・・・・・・・・もの。・・・・・・・・・・・・・・・・・・もの。・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
「・・・・・・・・・・・・・・・もの。・・・・・・・・・・・・・・・もの。・・・・・・・・・・・・・・・・・・もの。・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
心臓が一気に縮み上がったような感じだった。
こめかみの欠陥が脈打ってるのがはっきりわかった。
そのうち、窓ガラスが叩かれるようになった。
こんこん、こんこんという音とともに、「・・・・・・・・・・・・さい。・・・・・・・・・・・・さい。」という声が聞こえる。
ふと弟のほうを見るといつの間にか起きていて、真っ青な顔で「にいちゃん、あれなんだろ。怖いよ」と震えている。
俺は弟のそばにより、そして窓の声へと集中した。
「あけてください。・・・・・・あけてください。」
その声は、そういっていた。
声色は、やはり人間の赤ん坊のものだった。
しかし、窓の外の影はとても幼児、いや人間のものではなかった。
しかし、その声をずっと聞いているうちに、こいつも必死なんだなという妙な気分になってきた。
と、弟が「ダメだよ、兄ちゃん!」と。
ハッ、と我に返った。
俺はいつの間にか、窓に近寄って空けようとしていたのだ。
一気に恐怖が戻ってきて、そのまま弟のところまで這って戻り、今度はひっしと抱き合った。
そのまま、まんじりともせず朝を迎えた。
とんとん、とふすまを叩く音がして、「じいちゃんだぞ、なんともないか、無事か」と声をかけてきた。
俺はすっかり疑心暗鬼に陥っていたけど、朝日も差し込んできたし、こちらからあけなければ大丈夫だろうと思い「無事だよ」とだけ答えた。
するとふすまが開き、じいちゃん、ばあちゃん、昨日のおばちゃんと、両親が入ってきた。
おばちゃんは「よう頑張ったたい、とにかく無事でよかった」といってくれた。
お札は白から鉄錆みたいな色になっていて、なぜかもとの半分ほどの大きさしかなかった。
それから俺たち兄弟は実家に戻り、二度とじいちゃん家を訪れることはなかった。
そのじいちゃんは母方のものなので母親はその霊能力者とも親交があるらしく、何度か実家のほうに来てもらった。
月日は流れ、俺が高1のとき、じいちゃんが死んだとの知らせが入った。
死因は、なぜか話してもらえなかった。
母親にあの「けもの」との関連を問いただしても、だんまりを決め込んで決して答えようとはしなかった。
ばあちゃんは、緩やかに痴呆が進んでいるらしい、とだけ聞いた。
結局、あの「けもの」との関連は判らずじまいだった。
今はただ、あの日の軽率な行動を悔いてばかりいる。
ばあちゃんの世話をするどころか、その死に目にも会えないのが、無念でならない。
これが、俺の話。


