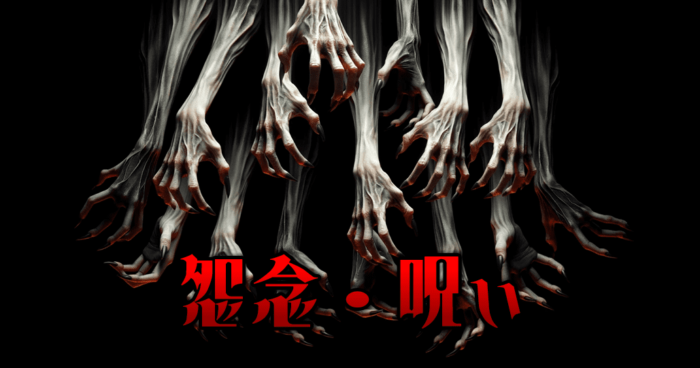俺は窓を少しだけ開けておくのが好きでね、寒さが厳しい季節以外はだいたい10センチくらい空けておく。
まあ単純に外の音とか臭いが好きだからなんだけど。
あのときも、いつも通り窓を少しだけ開けてテレビを見てた。
春先だったからときどき生温い風が入ってきた。
カーテンがヒラヒラ揺れてね。
午前1時過ぎのこと。
どこか遠くで猫が鳴き出した。
春の風物詩。
発情期の猫は結構野太い声で鳴く。
うなるように、絞り出すように。
当時、俺が住んでたのはワンルームマンションの2階で、建物の向こうには小さな畑を挟んで深い森が広がっていた。
とは言っても、別に嫌な感じがするような森ではなくてね、風に吹かれてゆっくりと揺れる木々を見ていると、不思議と心が落ち着いた。
ふと気が付くと、猫の鳴き声が徐々に近づいてきていた。
よっぽど発情してるのか、かなりドスの利いた、低くて重たい鳴き声だった。
テレビの画面では見たことのない芸人が笑えないコントを続けていた。
まるで取って付けたような客の笑いが空々しく響き渡っていた。
少し眠たくなる。
「あ゛あ゛あ゛あ゛ぁぁぅ・・・」
一瞬、身体がビクリと硬直した。
猫だ。
猫が、窓のすぐ外で、鳴いている。
いや、ちょっと待てよ。
このマンションにはベランダがない。
窓の外にはアルミ製の手すりがあるだけだ。
おまけにここは2階じゃないか。
「おあ゛あ゛あ゛あ゛ぁぉぉぉ・・・」
いや、これは、猫の声じゃない。
人だ。
人間の声だ。
そう思った瞬間、全身に鳥肌が立った。
あまりの緊張感で身体が動かない。
俺はありったけの勇気を振り絞り、窓のほうに目をやった。
誰かが、そこにいる。
カーテンは微動だにしていなかった。
テレビのスピーカーから空虚な笑い声が響いた。
部屋の空気がピタリと動きを止めた。
「あ゛あ゛ぁ・・・」
「誰だ!」とっさに俺は立ち上がって窓際に走り寄ると、力任せにカーテンを開けた。
目が合った。
窓のすぐ外にいたあいつと、わずか30センチの至近距離で目が合ってしまった。
それは生きた人間の目ではなかった。
ライチのようなドロリとした質感をしていた。
「・・・ぃぃぃぁぁあああ」
俺は口を大きく開け、まるで猫のような甲高い声を上げていた。
そのあいだも目を逸らすことができなかった。
身体は凍りつき、両手が大きく震えた。
恐いなんてものじゃない。
あれは絶対に見てはいけないものだった。
数秒後、俺は腰から砕けるように後ろに倒れた。
硬直した右手で掴んでいたカーテンがバチバチと大きな音を立てて外れた。
目覚めると朝だった。
窓の外には気持ちの良い青空が広がっていた。
俺の右手にはまだカーテンがしっかりと握り締められていて、一方のカーテンの端がかろうじてカーテンレールに引っかかっていた。
後日談。
大家の話では、その数年前、マンションの前の森で首吊り自殺があったらしい。
首を吊ったのは20代の女性で、失恋を苦にしての自殺だったそうだ。
新聞にも載ったのだという。
俺が引っ越してくる直前の出来事だったようだ。
なるほど。
世の中色んなことがある。
時には想像を絶する恐怖も。