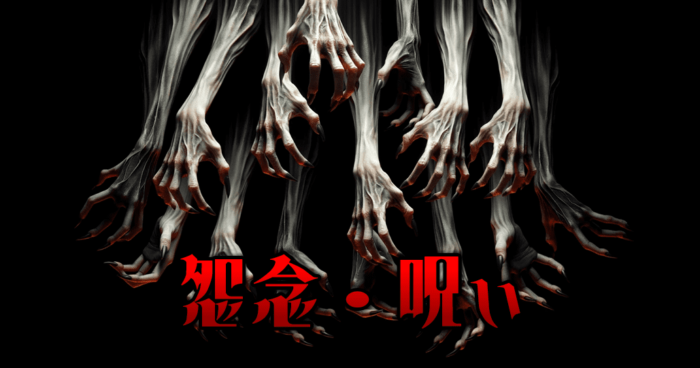全くお気楽な学生だったころの話。
季節はまさにお盆。
新しい彼女ができて、長年付き合った彼女と別れた。
しかし、元彼女の悲しむ姿を放っておけず、最低なことに元彼女の部屋にズルズルと連泊していた。
私は祝祭日や年中行事といったものに全く疎い人間である。
ある夏の夜、元彼女は既にスヤスヤと就寝していた。
私は彼女に気も使うことなく、彼女はさぞ眩しいだろうに、電気をつけたまま元彼女のPCでパチパチとチャットを楽しんでいた。
冷房が快適でとても過ごしやすい部屋だったが、午前3~4時ごろだろうか、急激になぜだかとても重苦しい気分が私を圧迫し始めた。
「さて、眠気かな」とも思ったが、重苦しい空気は物凄い勢いでより強く私を包み込もうとするように感じられた。
広めの6畳の部屋にいるのは私と元彼女だけなのだが、私は部屋には大勢の気配を感じた。
何人いるかはわからない、相当人数いそうだ。
私は身の回り一周をキョロキョロとなんども見渡したがなにも見えなかった。
しかし、部屋の空気が歪んで行くようなただならぬ雰囲気が充満していた。
「いや、俺は大分参っているらしい」と何度も冷静になろうとしたが、場の雰囲気はより一層耐え難いものになってくる。
得体の知れない見えない集団が私を押しつぶそうとしている、となぜだかわかった。
説明はできない。
体的な痛みでもなく、精神的痛みでもなく、適当か解らないが、「肝が絞り上げられる」ような不快感が高まった。
窒息しそうなほど息苦しくなった。
「対抗しなければヤラレル!」という動物的な興奮を憶えた。
異質な存在をビリビリと感じて霊体験にびびるというより、自分が敵意あるモノに囲まれた危険な状況にある、と直観した。
彼女はこちら側に背中を向け、スヤスヤと幸せそうに眠っている。
なんらかの反応行動を取りたくなかったのでずっとチャットしているノートのキーに手を置いたままでいた。
押しつぶされそうな感覚に「もう我慢の限界だ!!」と目を強く瞑った。
そのとき、右斜め前に、口を外側にあけて逆さまにひっくり返して放置してあったダンボールが「ボン!ドカン!」と鳴り始めた。
ちょうど、ダンボールをパンチしたり思いっきり蹴飛ばすとそんな音がでるだろう。
私は驚いて、いつでも一足飛びに飛び跳ねることができるように腰を浮かす体勢をとる。
今考えれば恐ろしいがダンボールに顔を近づけ神経を集中して観察した。
音源でありそなダンボールは微動だにしないのに、音がする。
心底驚いてはいたが大層不思議に感じた。
それはいいとして私を圧迫し押さえ込もうとする空気は最高潮に達してきて限界を越えた私は「うわーーーー」と叫び、眠りこけているその元彼女を揺すり起こした。
元彼女「・・・ぅぅなに?・・・どしたの?ムニャムニャ・・・」
私「何かおかしいよっここ!」
女「んんん・・・んん!?ぁっれー、なんでこんなにいっぱい人がいるの?」と寝ぼけまなこで元彼女はいった。
私「ええ!?どこに?え?だれが?」
私は元彼女が被っていたタオルケットを剥ぎ取り、頭からすっぽり被りこんでベッドで丸くなって震えた。
私がひどく怯えてガタガタ震えているのを見た元彼女はそんな私が珍しいのか、ひどく滑稽なものをみるように元気良くケラケラと笑い、「あー、もういなくなったよ?うん。いないいない。帰ったみたい」といった。
「は?え?」と思ったが、とにかく無心に彼女に抱きついてベッドに入った。
いつもはひどく怖がりなその元彼女は、ひどく狼狽している私を落ち着かせるために私をトントンと叩きながら。
「そういえば、今日お彼岸の日だよね。鹿鳴館に出てくるような格好した人たちが大勢いたよ」とポツリといった。
元彼女の先祖の系統で、戦前に総理大臣がでたんだよ、という自慢を前に聞いていた。
お彼岸の日に、元彼女はよく似たような霊をみたり身近に感じるといった。
それは怖くないらしい(他は全く霊感働かないらしい)んんん・・・。
後日、「俺ってやっぱ歓迎されてないんだろうな、元彼女の祖先の霊たちに・・・」と一人で納得した。
今考えてみて、私が浮気しても散々振り回しても彼女は常に笑顔で元気に振舞っていた。
彼女はどれくらい苦しんだのだろうか・・・心が痛む。
私をやりこめたのは、誇りある祖先なら当然だ、私は心の中で謝罪した。