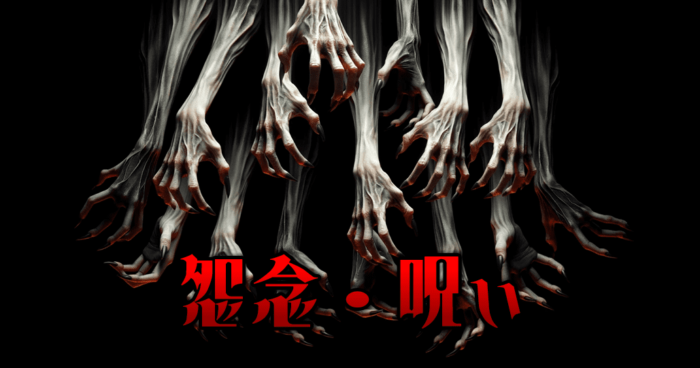昔、姉の本棚にあった多田かおる短編集から『ピンクの雪が降ったら・・・』を読んだのが10年くらい前なので、ところどころ脳内補完されているかもしれない。
主人公は夫と老猫と暮らす若い主婦。
新婚早々から夫が出張に出掛けることにすねている。
夫はそんな主人公をなだめ、軽くイチャついてなんとか機嫌を直し、飛行機に遅れてしまうと急いでタクシーに飛び込んだ。
夫を見送った主人公がいつものように家事をこなし一段落ついてテレビをつけると、飛行機事故のニュースが放送されていた。
乗員乗客に生存者の見込みはないとアナウンサーが言う。
乗客のリストが次々とテレビ画面に映し出され、その中には夫の名前もあった。
あまりの出来事に主人公は呆然としたまま数時間が過ぎた。
すると、なんとそこへ夫が帰ってきた。
「時間ギリギリに家を発った上にタクシーが渋滞に巻き込まれて、結局飛行機には間に合わなかったんだ」と夫は言う。
事故でごった返す空港からは電話もかけられなかった(※携帯電話が一般的ではない時代)とのこと。
主人公は一安心して夫の無事を喜ぶ。
翌日からいつも通りの幸せな日々が再開した。
しかし、飛行機事故のあった日から、夫は少しだけ変わったような気がした。
相変わらず主人公に優しい夫なのだが、少し寒がりになり、食べ物の好みが変わったようだった。
主人公はそんな夫を不思議に思うが、『それ以上に気がかりなこと』があったので夫の変化を深く考えることはしなかった。
主人公の気がかりとは、飼っている老猫が飛行機事故の日以来帰ってこないことである。
年老いて随分大人しくなった猫が、今までこんなに長く留守にすることは無かった。
ある日、帰ってこない老猫のことを夫に相談すると、「あいつも年だし、猫は死ぬとき姿を消すとも言う。探さない方がいいんじゃないか」等と言う。
それが原因で主人公と夫は喧嘩をしてしまう。
気まずいまま出勤する夫を見送った。
老猫は主人公が子供の頃から飼っていた猫で、夫との馴れ初めも、迷子になった猫を探すのを手伝ってもらったことだった。
独身時代は猫を連れてデートにも行ったし、結婚してから猫も家族の一員だったのに、夫は心配してくれないのか・・・。
と、思い悩む主人公の元に実家の母から電話がかかってくる。
母曰く、「夫くんのお葬式にも出ないで落ち込んでいるようだけど、大丈夫なの?」
夫は生きているのに何を言うのか、と主人公が返すと、「まだ新婚なのにこんなことになって・・・辛いだろうけど現実を見なさい。夫くんは飛行機事故で亡くなったでしょう?あなたはまだ若い、とにかく一度実家に帰っておいで」と、そんな内容を繰り返して電話は切れた。
混乱し不安になった主人公は、とにかく夫と話そうと勤務先に電話を掛ける。
「○○さんの奥様ですか?・・・この度は本当に御愁傷様でした・・・」
今日も出勤しているはずの会社でも、夫は死んだことになっていた。
考えてみると、飛行機に乗り遅れたというのも不自然だし、事故の日以降、夫の様子はずっと変だった。
あの飛行機事故で夫が死んだというのなら、あの日から昨日までここに帰ってきた『夫』は何者なのか?
やがて帰ってきた『夫』に主人公は問いつめる。
「夫は飛行機事故で死んだんでしょう?あなたは夫じゃないでしょう?なんで夫のふりをして私に近づいたの?騙したの?あなた誰なの?何が目的なの?」
激昂(げきこう)する主人公に、『夫』は寂しげに笑って、「昔、ピンクの雪が降ったら言うこと聞いてくれるって君は言ってたけど、覚えてる?一人でもちゃんと生きてくれ。それが俺の願いだ。」
それだけ言って部屋を飛び出した。
なにひとつ疑問の答えをくれない『夫』を追って主人公も走る。
だが主人公が追い付く前に『夫』は車道に飛び出し、あたりにブレーキ音が響いた。
人を轢いたと思って急いで降りてきた運転手は回りを見渡すが、道路に横たわっているのは夫ではなく、主人公が飼っていた老猫だった・・・。
夫が飛行機事故で死んだあと、夫に成り済ましていたのは主人公の飼っていた老猫だった。
主人公は、まだ恋人だった頃の夫が隣にいて、まだ若く元気だった頃の猫を胸に抱いていた日のことを思い出す。
降りだした雪にはしゃいだ主人公は確かに言った。
「ピンクの雪が降ったら、あたしなんでも言うこと聞いてあげる!」
主人公は猫の亡骸を抱いて、夫の姿で猫が最後に言ったことを思い涙する。
『昔、ピンクの雪が降ったら言うこと聞いてくれるって君は言ってたけど、覚えてる?一人でもちゃんと生きてくれ。それが俺の願いだ。』
降りだした雪は、飛び散った老猫の血で薄くピンク色に染まっていった。
猫は主人公の為を思って夫に化けたのはわかるんだが、おかげで主人公は夫の葬式にも行けなかったのか・・・とか思うと、後味悪いと言うよりひたすら悲しい。